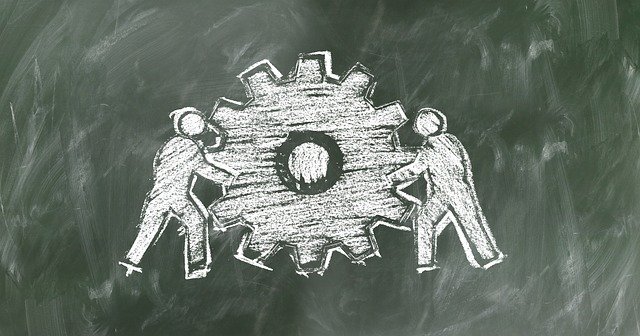臨床心理士×プロ家庭教師の家庭教師カウンセラーが心理学の問題を作りました。
大学院入試や心理学検定の力試しとしてご活用ください。
今回は産業・組織心理学の中から【ホーソン実験】についての【正誤(マルバツ)問題】です。
大学院入試では基礎心理学分野、心理学検定ではB領域(産業・組織)に該当します。
それではがんばってください。
問題
問題1
ホーソン実験の背景について述べた文のうち適切でないものはどれか。
- ホーソン実験はイリノイ州ホーソンにある電話会社の製造工場で行われた実験である。
- ホーソン実験の目的は人間関係論に基づく生産効率の改善である。
- 最初は、作業環境の変化が作業能率に及ぼす影響についての検証実験が行われた。
- 作業時間や労働条件と生産性の関係を見るための実験はハーバード大学の研究者が参加したのちに行われた。
問題2
ホーソン実験における照明と生産性の関連について適切でないものはどれか。
- 照明の明るさと生産性の関係の調査はホーソン実験において最初に行われた実験である。
- 照明の明るさ・暗さによって生産性に差が生まれると予想されていた。
- 作業室の照明を明るくしても暗くしても作業員の生産性は向上しなかった。
- 作業員たちには、照明が暗くなると(作業環境がわるくなると)それを努力によって補おうとする傾向が認められた。
問題3
女性作業員たちを被験者とする電話交換機用継電器組み立て作業実験について述べた文として適切でないものはどれか。
- 実験にはハーバード大学の研究者が参加した。
- 参加したハーバード大学の研究者はTaylor, F. W. とRoethlisberger, F. J. である。
- 実験は1927年から5年間続けられた。
- 実験は条件を変化させながら、組み立て作業の様子や生産量が観察および記録された。
問題4
ホーソン実験の手続きと結果として適切でないものはどれか。
- ホーソン実験は、照明実験、リレー組み立て実験、面接調査の3つからなる。
- 感情や人間関係が生産性に大きな影響を及ぼすことがわかった。
- 組織の中での注目や承認がモチベーションを上げるという現象はのちに「ホーソン効果」と呼ばれるようになった。
- 実験を終えて、物理的な作業環境よりも職場における人間関係や目標意識が作業能率を左右するのではないかという仮説が成り立った。
問題5
ホーソン実験の意義について適切でないものはどれか。
- 従来の科学的管理法における経済的な人間観に対し、社会的人間観を重要視する流れを生み出した。
- 作業員の態度や能率は、職場という公式集団における人間関係や仲間意識に大きく影響されているとわかった。
- 産業場面に社会心理学的な観点が導入され、人間関係論(human relations)が展開するきっかけとなった。
- モラール、動機づけ、リーダーシップなど現代でも重視される多くの研究が生まれるきっかけとなった。
解答・解説
解説の黄色いアンダーラインは適切な文章であることを表します。
問題1 ホーソン実験の背景
正答:2
- ホーソン実験はイリノイ州ホーソンにある電話会社の製造工場で行われた実験である。
- ホーソン実験の目的は人間関係論に基づく生産効率の改善である。→誤り。ホーソン実験の目的は科学的管理法に基づく生産効率の改善。
- 最初は、作業環境の変化が作業能率に及ぼす影響についての検証実験が行われた。
- 作業時間や労働条件と生産性の関係を見るための実験はハーバード大学の研究者が参加したのちに行われた。
問題2 ホーソン実験(照明と生産性の関連)
正答:3
- 照明の明るさと生産性の関係の調査はホーソン実験において最初に行われた実験である。
- 照明の明るさ・暗さによって生産性に差が生まれると予想されていた。
- 作業室の照明を明るくしても暗くしても作業員の生産性は向上しなかった。→誤り。明るくなっても暗くなってもどちらも生産性が向上した。
- 作業員たちには、照明が暗くなると(作業環境がわるくなると)それを努力によって補おうとする傾向が認められた。
問題3 女性作業員たちを被験者とする組み立て作業実験
正答:2
- 実験にはハーバード大学の研究者が参加した。
- 参加したハーバード大学の研究者はTaylor, F. W. とRoethlisberger, F. J. である。→誤り。参加した研究者は Mayo, G. E. と Roethlisberger, F. J. である。(メイヨーとレスリスバーガー)
- 実験は1927年から5年間続けられた。
- 実験は条件を変化させながら、組み立て作業の様子や生産量が観察および記録された。
問題4 ホーソン実験の手続きと結果
正答:1
- ホーソン実験は、照明実験、リレー組み立て実験、面接調査の3つからなる。→誤り。ホーソン実験の内容は照明実験、リレー組み立て実験、面接調査およびバンク配線作業実験の4つである。
- 感情や人間関係が生産性に大きな影響を及ぼすことがわかった。
- 組織の中での注目や承認がモチベーションを上げるという現象はのちに「ホーソン効果」と呼ばれるようになった。
- 実験を終えて、物理的な職場環境よりも職場における人間関係や目標意識が作業能率を左右するのではないかという仮説が成り立った。
問題5 ホーソン実験の意義
正答:2
- 従来の科学的管理法における経済的な人間観に対し、社会的人間観を重要視する流れを生み出した。
- 作業員の態度や能率は、職場という公式集団における人間関係や仲間意識に大きく影響されているとわかった。→誤り。職場という公式集団ではなく、人間関係や仲間意識といった非公式集団(informal group)によって作業員の態度や能率は影響されるとわかった。
- 産業場面に社会心理学的な観点が導入され、人間関係論(human relations)が展開するきっかけとなった。
- モラール、動機づけ、リーダーシップなど現代でも重視される多くの研究が生まれるきっかけとなった。
おつかれさまでした!
勉強がんばってくださいね^^
参考文献・参考サイト
ホーソン実験(HRプロ)
ホーソン実験(コトバンク)
ホーソン効果(コトバンク)
フレデリック・テイラー VS エルトン・メイヨー(日創研)
ホーソン実験とは生産性の実験!工場での実験から判明した結論を簡単に解説!(HRBrain)
このページの問題を作るにあたり参考にした文献をご紹介します。
どれも必携の良書ですのでぜひお手にとってみてください。
ご覧いただきありがとうございます。
院試対策のオンライン家庭教師
大学生さんの学習支援
随時、承っております。
お問い合わせはお気軽に^^
→家庭教師カウンセラー メールフォーム
image photo:https://pixabay.com/images/id-2499632/